みなさんこんにちは。SaveExpats広報です。
SaveExpatsは、海外駐在員が安心して現地で活躍できる環境づくりを目指して活動しています。このコラムでは、駐在員を支える海外人事の皆様に向けて、日々の業務に役立つ情報をお届けしています。
さて、実務のポイント第6回目は、「出向契約・人件費請求」について考えていきたいと思います。
駐在員を海外に派遣する際、現地法人との関係性によって、その赴任形態は異なります。
駐在員事務所や海外支店での勤務と、現地法人への出向では、手続きや費用負担の考え方が大きく異なります。特に、出向契約を締結する場合、契約内容の整理や人件費請求の方法について慎重に検討する必要があります。
今回のコラムでは、海外駐在員の出向契約の基本、費用負担のポイント、そして実務上の課題について解説していきます。
海外赴任の形態と特徴
最初に自社の社員が海外に赴任し、仕事をする際の形態について整理してみます。形態は大きく3つに分類されます。駐在員事務所や海外支店の設置、現地法人を設立といったものです。それぞれ大まかな特徴を見てみましょう。

駐在員事務所
駐在員事務所は、日本本社の一部として設置されます。主に連絡業務、情報収集、市場調査、広報活動、販売代理店の支援など、営利を目的としない業務を行います。手続きが比較的簡単で設立しやすいのが特徴です。ただし、営業活動は認められておらず、収益を上げることはできません。
海外支店
海外支店は、進出国で代表者を定め、登記などの手続きを経て設立されます。支店の活動は本社の一部とみなされ、営業活動を行うことが可能です。ただし、支店の法律行為や責任はすべて日本法人が負うことになります。また、国によっては支店の設置が制限される場合もあります。
現地法人
現地法人は、進出国の法律に基づき独立した法人として設立されます。
事業の自由度が高い一方で、現地の法律に従い、取締役や従業員を雇う義務が生じることがあります。また、外資規制がある国では、一定の制約を受けることもあります。設立には時間と資本金が必要となるため、進出時のコストや手続きの負担は最も大きくなります。
転勤と出向の違いと特徴
駐在員事務所や海外支店は、場所が海外にあるというだけで、同じ会社の別拠点ですので「転勤」という扱いになります。
一方で子会社やグループ会社といった現地法人に社員が赴任する場合には、法的には別の会社に行って仕事をすることになりますので「出向」という取扱いになります。
出向の定義と仕組み
出向の定義は社員が元の企業に在籍のまま、他の企業の社員となって長期間にわたって出向先企業の仕事をすることです。社員は出向元と出向先の2つの企業と二重に雇用契約を結ぶ状態となり、出向期間中は出向先の指揮命令に基づいて仕事をします。

海外転勤の手続というのは、ビザの取得などを除いて基本的に社内で完結しますが、一方、出向となると、異なる企業間での人の往来ですので、出向契約を締結し、出向社員の取扱いや費用負担など、さまざまな内容について明確にする必要があります。
出向社員には人件費のほかにさまざまな費用が発生します。出向社員は出向先の仕事を行うのですから、掛かる費用は労務の提供を受ける出向先企業が負担することが原則です。
出向契約書には海外駐在に起因するコストをすべて洗い出したうえで、費用負担の項目を設け、それらを出向元、出向先のどちらで負担するのかを定めておく必要があります。
出向契約の実務上の課題
このように文章で書くと簡単に思えますが、実務はそんなに簡単ではありません。
第一に海外駐在員に支払う給与や賞与、社会保険料などの人件費をはじめ、赴任準備にかかる費用や赴任中に発生する駐在員ならではの経費など、その多くが日本で支払いが発生するということです。
特に、海外駐在員の給与や賞与、社会保険料などの人件費に加え、赴任準備にかかる費用や赴任中の駐在員特有の経費など、多くの支払いが日本国内で発生する点が挙げられます。
第二にそれら駐在員に関するコストを合計すると、日本勤務時の2~3倍程度になることも珍しくなく、この金額の大きさが出向先の現地法人側から見て、想定より非常に高いものに感じられることが挙げられます。
また、駐在員ならではの取扱いに関するコストについては、その必要性や妥当性について理解を得る難しさがあります。
単独資本で進出であればまだしも、JVで現地パートナーがいる場合など、その難易度は一層高くなります。また、国によっては外貨の国外流出を懸念して、海外送金に規制をかけていて、請求しても支払えないケースもあります。よって、出向契約における費用負担については、それら実態を踏まえて費用負担を決定することになります。
一方、日本の国税当局の移転価格税制についての調査などでは、海外駐在員にかかるコスト負担の妥当性が問題視されるケースが多く、最悪の場合、寄附金に該当し損金算入を否認され、追徴課税される場合もあり、海外人事担当者はこれら相反する利害関係の中で悩むことになります。

出向契約書の内容が合意され締結されると、今度はその契約書の費用負担に沿って、実際に駐在員にかかった費用を請求することになります。
常時駐在員を数百人規模で抱えている企業ならまだしも、多くの企業はそこまでのボリュームはない場合が多いと思います。その場合、専用のITシステムなどを構築しているケースは少なく、多くの企業では、表計算ソフトなどを使った手計算で請求金額を集計しているのが実情です。
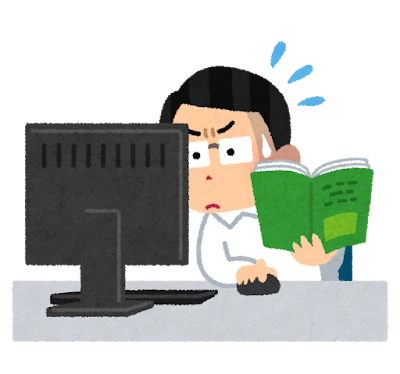
これら費用集計の実務においては、契約書がきちんと整備されルールがはっきりしている場合には、ITツールを使うことで業務効率の向上が期待できます。VBAや業務アプリなどを利用してRPA(ロボティックプロセスオートメーション)を導入することで、同時に業務品質の向上も実現したいものです。
これら海外駐在員の出向契約に関する課題としては、駐在コストの計算は給与など処遇、制度などを熟知している人事部門にしか現実的にできません。しかし前述のとおり税務の専門家ではないため、独学で勉強しないかぎり、そこまでの専門性をもつことは難しいといえます。
一方で社内の経理財務部門には、税務の専門性を持ったスタッフはいますが、逆に駐在員に関する人事制度に詳しいケースはまれであり、ほとんどの場合、駐在員にかかるコストを包括的に把握することは不可能だといえます。
したがって、海外駐在全体をスムーズかつ適法に実施するためには、全体像を理解できる人事部門がイニシアチブをとって、関係部門を巻き込んで仕組みづくりを行う必要があるといえます。

見方を変えると、海外駐在員を派遣して重要なビジネスを推進してもらい、事業を計画どおり運営してもらうということは、会社経営の根幹に関わるレベルといえます。
人事部門にいながら将来のキャリアを見据えた貴重な経験ができる、稀有なポジションといえるのではないでしょうか。
