みなさんこんにちは。SaveExpats広報です。
SaveExpatsは、海外駐在員が安心して現地で活躍できる環境づくりを目指して活動しています。このコラムでは、駐在員を支える海外人事の皆様に向けて、日々の業務に役立つ情報をお届けしています。
さて、実務のポイント第7回目は、「危機管理」です。わが国で生活していると地震や台風などといった自然災害をイメージすると思いますが、海外での生活ということを考えると、想定されるリスクはそれだけにとどまりません。
世界でここ数年に起きた出来事を思い起こしてみましょう。
新型コロナウイルスによるパンデミックや、21世紀にまさかの戦争、クーデターやテロなど、そのほとんどが我々の日常生活では想像できないものばかりです。
元気に帰ってくることが一番重要です。
社員に海外に駐在してもらい、ビジネスを成功に導くための最低要件は、安全で健康に現地で生活し、任期を全うして元気に帰ってくることです。

労働災害の発生頻度が多い業種の事業所には「安全第一」や「安全は生産に優先する」などといった標語が掲げられており、それを目にしたことがある方も多いと思います。
一見すると「なにをあたり前のことをいまさら」と思うかもしれませんが、そのあたり前を実現するために、これら業種においては、国内においてもさまざまな努力がなされています。それほど、仕事において安全というのは重要なものなのです。
駐在員の現地生活における安全を確保するためには、まずリスクの洗い出しを行い、それに対する対策を講じていく必要があります。
それではリスクの洗い出しはどのように行うべきなのでしょうか。
BCMとの連動
海外に駐在員を置くレベルの企業であれば、BCM(事業継続マネジメント:business continuity management)の仕組みを構築し、運用しているケースがほとんどと思われます。
BCMとは、想定されるリスク発生時に、早急に事業活動を復旧させ、経営に対するインパクトをいかに最小限にするという目的で策定された経営マネジメント手法のことです。
防災活動との関係性から主な目的を比較すると以下のように整理されます。
企業の従来の防災活動:身体・生命の安全確保、物的被害の軽減
BCM:身体・生命の安全確保に加え、優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続または早期復旧
出典:内閣府「事業継続ガイドライン」
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03.pdf
BCMというと、事業活動の早期復旧という点に目が行きがちですが、その前提条件として社員の「身体・生命の安全確保」が掲げられています。したがって海外人事としては、会社でオフィシャルにBCMで仕組み化されているリスク項目の洗い出しと、対応をしっかりと理解して主体的に参画していくことが第一歩といえます。

BCMは経営企画や事業部といったビジネス側の主導で推進されることが多く、ともすると受け身スタンスのやらされ仕事になってしまいがちですが、駐在員の安全の確保という観点でも非常に重要です。海外人事の担当者としては、理解を深めてしっかりと対応していきたいものです。
情報格差
そのうえで、海外駐在員の安全を守るためのポイントはどのようなものでしょうか。
国家体制や政情の不安定さ、治安の悪さなどが真っ先に思い浮かびますが、特に重要なのは海外特有の事情である情報格差です。
ネットやスマートフォンの普及で以前に比べるとかなり改善されていますが、それでも日本での生活に比較すると情報の量、スピードともに劣ると言わざるを得ません。
海外生活で安全を確保する場合の情報は2種類に分類されます。
まずひとつ目は近い将来のリスクの可能性を評価するための世界情勢などの動きです。これらは現在ではネットにより、信頼できるサイトなどを通じて広く収集することが可能となってきました。
2つ目は緊急時における速報性の高い情報です。
戦争、クーデターやテロ、そして自然災害などの情報は、駐在員自身が現地で身を守るために、事前に策定されている会社の方針を踏まえ、その場で自ら判断するためになくてはならないものです。
これらの情報を得るために頼りになるのは、やはり日本国の機関である外務省でしょう。外務省設置法には、その所管事務として「海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること」と明記されています。
外務省の海外安全ホームページには、海外駐在員向けの様々なサービスが掲載されています。その中でも情報収集の手段としてとくに有効と思われるのは、「たびレジ(海外安全情報無料配信サービス)」です。これは海外生活での安全確保を考えたときに外すことができません。
また、「海外進出企業向け 海外安全対策セミナー」なども定期的に開催されています。安全確保手段の検討や、最新情報のアップデートなどにも役立ちますので、参加して情報収集に役立てたいものです。
PDCAを回していく
ビジネスに限らす海外に目を向けてみたときに、わたしたちがもう一度考えなければならないのは、「日本人は検証、総括が苦手」ということです。
コロナ禍におけるわが国政府の対応について、あらためて検証し、次に同じようなことが起きたときにどのようにすべきか、という話はあまり聞こえてきません。
これは多くの企業にも当てはまることで、「のど元過ぎれば」で終わってしまっているケースはよく聞く話です。はじめて経験する事象では、多くの想定外のことが起こります。その教訓を活かし、学習することで、組織にノウハウが蓄積され、レベルが向上していきます。
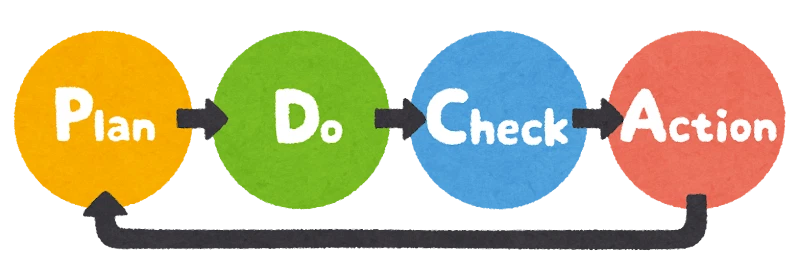
これは危機管理に限ったことではありませんが、PDCAを回していくことを体質化して組織レベルがつねに向上する風土や文化を醸成していくことも人事分門としては重要な役割のひとつといえるのではないでしょうか。

